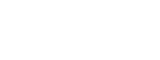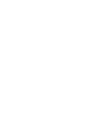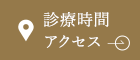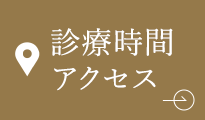大腸憩室症とは?
大腸憩室症とは、大腸の壁の一部が外側に袋状に飛び出した「憩室(けいしつ)」ができる状態をいいます。加齢や便秘、食生活などが関係しており、中高年の方を中心に増えている病気です。多くの場合、憩室があっても症状はありませんが、炎症(憩室炎)や出血を起こすこともあり、注意が必要です。
憩室ができる原因
憩室は、以下のような要因によって作られると考えられています。
- 加齢による腸壁の弱化
- 便秘やいきみなどによる腸内圧の上昇
- 食物繊維の不足
- 肥満や運動不足、喫煙
憩室は、大腸の中でもS状結腸(左側)や上行結腸(右側)にできやすいです。日本人では右側に多く、欧米では左側に多い傾向があります。
大腸憩室症の種類
- 単純性憩室症:憩室があるだけで症状はない状態。
- 憩室炎:憩室に細菌感染や炎症が起きて、腹痛や発熱などの症状が出ます。
- 憩室出血:憩室から突然出血し、血便が出ることがあります。
主な症状
憩室があるだけでは無症状ですが、炎症や出血が起きると次のような症状が出ます。
- 左下腹部または右下腹部の痛み
- 発熱
- 便秘または下痢
- 血便(鮮やかな赤い血が便や紙につく)
- 腹部の張り・違和感
診断方法
以下の検査によって、大腸憩室症かどうかを診断します。
- 大腸内視鏡検査(大腸カメラ):憩室の位置や数、炎症や出血の有無を確認。
- 腹部CT検査:炎症の広がりや合併症(膿瘍、穿孔)の有無を評価。
- 血液検査:炎症反応や貧血の有無を確認。
治療方法
無症状の場合(単純性憩室症)
- 特別な治療は不要ですが、食物繊維の摂取や便通の改善が大切です。
- 定期的な経過観察をおすすめします。
憩室炎の場合
- 軽症:抗菌薬の内服や食事制限(絶食〜消化の良い食事)
- 重症:点滴治療・入院管理、場合によっては手術が必要なことも。
憩室出血の場合
- 出血が自然に止まることも多いですが、止まらない場合は内視鏡的止血処置を行うことがあります。
再発予防のために
憩室炎や出血は再発しやすいため、以下のような予防が重要です。
- 便秘を防ぐ生活習慣(食物繊維・水分の摂取)
- 適度な運動
- 規則正しい食生活
- 禁煙
当院の対応について

当院では、大腸憩室症の診断から治療、再発予防のアドバイスまで一貫して対応しています。